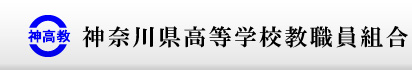ホーム > 機関情報 > ワークライフバランス−わたしたちの権利手帳 > 家族が病気したとき
家族が病気したとき◆短期介護休暇◆ 〈有給、臨任・非常勤は勤務時間数及び雇用期間に応じて一部無給 (子の看護休暇と同様)〉
Q 母が急に体調をくずし、 病院に付き添って行かなければならなくなりました。 こんな時も短期介護休暇がとれますか。 A 要介護者の要件として、 2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者となっています。 要介護の状態であったとしても、 請求者本人が介護をしていたかどうかが、 取得条件ではありません。 ただし、 請求者本人が介護又は世話をすることが、 取得条件です。 なお、 要介護者の状態等申出書には、 2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるということを、 具体的に記載することが必要です。 Q 介護休暇とどう違うのですか。 A 介護休暇は、 一定の期間 (連続する2週間以上、 6ヵ月以内) で、 日または時間を単位 (始業または終業の時刻に連続した4時間の範囲内) とし、 計画的に取得する必要があり、 原則1週間前に届け出なければなりません。 さらに無給です。 (下記参照) ◆介護休暇◆ 〈無給〉
※勤務時間の短縮 (1日7時間45分) に伴い、 時間単位での取得の場合の残り (分単位) のとりあつかいについては、2009.5現在交渉課題となっています。  Q 連続する6ヶ月のうちにおいて断続的にとることができますか? A 連続する6ヶ月の期間内であれば連続して、 あるいは断続して取得することが可能であり、 時間単位の取得も可能です。 例えば、 1週間の内特定の曜日だけをとるとか1日ごとに日単位と時間単位の休暇を繰り返してとることも可能です。 Q 一旦介護休暇を取った後、 同じ病気で再び介護休暇を取ることができますか? A 同一原因で複数回の介護休暇を取ることはできませんが、 病気が治った後、 再発したものであれば、 認められます。 Q 父と母が二人とも病気になり介護を要する状況にあるのですが… A それぞれについて6ヶ月ずつ介護休暇を取ることができます。 つまり要介護者が複数いる場合は一人について6ヶ月の休暇を取ることが可能です。 Q 以前は同居していなかったのですが、 介護のため祖父の家に泊まりこみたいのですが… A 「同居」 の中には、1.介護のため要介護者宅に泊り込む場合、 2.入院中の要介護者を退院後自宅に引き取るような場合を含みます。 ただし、 夜間のみ泊り込んで介護する場合は含まれません。 Q 休暇中の代替職員は配置されますか? A 原則として療休2週間以上と同様に非常勤で措置されます。 Q 不登校の子のケア―に介護休暇を取ることができますか。 A 不登校というだけでは認められませんが、「疾病に起因し、 日常生活を営むのに支障がある場合」 にはとることができます。 ◆介護欠勤◆ 〈無給〉
Q 時間単位でもとれますか? A 時間単位の場合には、始業または終業の時刻に連続した4時間を限度に認められます。 Q 欠勤となることに抵抗がありますが… A 確かに、 欠勤ということばにはマイナス・イメージがあるかもしれません。 しかし、 給与については、 共済組合から、 給料日額の60%が支給されます (手続きが必要)。 その際の看護対象は、 被扶養者でなくても、 組合員の配偶者または一親等の親族 (子の配偶者を除く) であれば支給できます。 休業手当金については毎年配布される 「共済のしおり」 にも記載されています。 ◆育児・介護にかかわる時差出勤◆
Q 「特別な事情」とは具体的にはどういった場合認められるのでしょうか。 A 人工透析をうけているなど、混雑した交通機関を回避する必要がある人については認められます。 Q 時差出勤が認められなくなるのはどのような場合ですか。 A 育児については、子の死亡、離婚により子でなくなる、同居しなくなる、などが、また介護については、要介護者の死亡、関係の消滅、同居や同一生計の事実がなくなるなどが考えられます。 ◆介護を理由とした退職・再採用制度◆
Q 週に2日介護休暇をとり3月末で5ヶ月になります。 病状が悪化しているので、 退職したいのですが、 この制度はつかえますか。 A 介護休暇取得開始から1年以内であれば、 どのようなとり方をしていても対象となります。 介護休暇6ヶ月を使い、 その後介護欠勤を断続的に時間単位でとっていても、 介護休暇取得開始から1年以内なら対象となります。 Q 退職の時期、 再採用の時期は決まっていますか。 A 退職の時期は介護休暇取得開始から1年以内の任意の時期となりますが、 再採用の時期は原則として4月1日です。 Q この制度を利用して退職したのですが、 3年たっても介護が続きそうです。 再採用の対象となれないのであれば、 勧奨退職として扱うことはできませんか。 A 退職時の選択を変えることはできません |