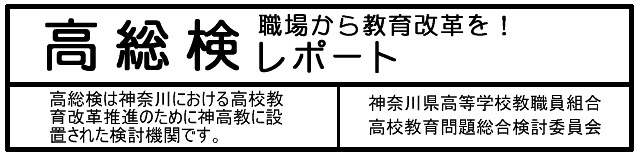
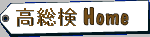
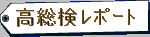
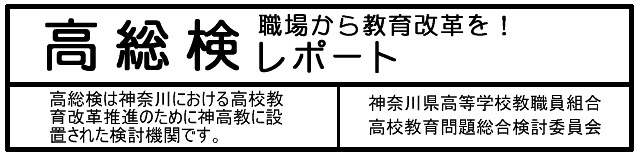
学級規模の縮小は先送りに
『中間まとめ』は、「現状と課題」の部で「生徒の多様化」という項を立て、「意欲をもって学習や部活動等に取り組む生徒がいる一方で、一部には目的意識や学習意欲に欠け、中途退学に至る生徒がいる実情もある。また、いじめや不登校、薬物乱用、性の逸脱行為なども深刻な状況にあるといえる。」という現状認識を示している(P.5)。しかし、それらをもたらしている原因がどこにあるかの分析はまったくなく、いきなり天下り式に次のような文部省直伝の全国一律“特色ある"高校づくりを持ち出す。
「今後も、県立高校においては、意欲と希望をもって高校ヘの進学を望む子どもたちに、幅広い進学の機会を確保するよう努めるとともに、これまで以上に、社会の変化や生徒の多様化に、きめ細かく対応する教育を展開していく…」。(すなわち)「生徒の学校選択の幅を広げ、様々な選択肢の中から、自らの興味・関心や進路希望等に適した学習内容を選択できるよう、弾力的な教育課程の編成など、特色ある高校づくりを一層推進し、県立高校の多様化を図るとともに、柔軟な学びのシステムを実現する必要がある」。
そして、「子どもたちが、望ましい環境の中で一人ひとりの個性を生かすことができる教育を受けられるよう、県立高校の規模、配置の適正化を図るとともに、教育環境や教育条件の一層の整備・充実を図る必要がある」と形ばかりに付け加えるのだが、強調されるのは、「生徒数の動向を展望した適正規模と適正配置」(P.16〜20)、つまり高校のリストラと「多様化」ばかりで、教育行政の固有の責務(教育基本法第10条)とされている「教育環境や教育条件の一層の整備・充実」にっいては、独立した項目も設けていない。わずかに、「再配置を踏まえた施設設備の整備」の項(P.18)で、「多様化」と高校の再編成・統廃合などを条件にした物質的条件の整備が触れられているのみである。
また、「教育環境や教育条件の整備・充実」で最も肝心の学級定員についても、その改善を無限定な将来の課題に棚上げしつつ、「国の動向など諸般の事情を勘案して」と中身のない官僚の常套句を前置きし「当面1学級40人とする」とためらうことなく断定している(P.17)。ちなみに、同じ箇所に、「学級定員を授業展開上の人数と必ずしも連動させる必要はなく」(学級定員自体の改善が行われなくても、「多様化」上のレッスン・クラスの編成やチーム・テイーチングなどで対応できる)という意味合いの表現があるが、言うまでもなく、現行法制では、各課程の生徒数に応して学級数が決められ、それに応じて教職員数が算出される仕組みになっており、学級定員の改善がなければ、原則として、教職員定数の改善もなされない。したがって、どのようなレッスン・クラスを完成しても、学級定員の改善がなければ、基本的に、教職員の労働強化なしには、教育条件がよくなることはない。『中間まとめ』はこのことに無知なのか、ごまかそうとしているのか。
ともあれ、人的・物的な教育条件の改革・改善をとおして今日の子どもと学校教育をめぐる深刻な危機の打開を図る、という考えはあらかじめ排除されているということだけは、『中間まとめ』全体からはっきり読み取ることができる。
待ったなしのダウンサイジング
学級規模の縮小は、教育行政に対する教職員の長年の中心的な要求項目である。しかし、教育・福祉分野ヘのー貫した低予算配分政策のもとで、それは遅々として進んでいない。また、この間題について幅広い世論の理解を得ることにも、教職員はあまり成功していない。
江戸時代以来、日本人の教育観には儒教的な精神主義が深く浸透しているが、国民皆学の学校制度が創設されてさほど年月を経ない明治中期に、富国強兵政策のため教育財源がさらに圧縮され、「非常に厳しい環境のなかで苦労しながら勉強し立身出世してゆく(「苦学」)という学習(観)が、(政府によって)かなり意図的に持ち込まれた」(喜多明人「学校施設の日本の特殊性」『教育』1990年11月号)。「蛍の光・窓の雪(明かりで)文読む月日重ねつつ…」また、人を教え導くという尊い営みに待遇・報酬を間わずよろしく献身すべしとする教師=聖職者観も同じ時期に定着する(聖職論の内実は、待遇を問わず献身するという部分にある)。国民の頭に刷り込まれたこの固定観念は大正を経て昭和の大戦後にも生き残る。「我が国の学校の建物がなぜ美しくないかという理由は、金の間題というよりは、むしろ教育に対する考え方の問題である場合が多い。すなわち不自由な環境のもとにあるほど教育の効果が上がるという考え方が支配的であった」(文部省、前掲書所収)。このような「考え方」は、根っこのところでは、現在も変わっていない。たとえば、公共施設の建築単価のうちでー番低いのが学校のそれである。学級定員・教職員定数の改善(第7次義務教育諸学校・第6次高校教職員定数改善計画)についても−もともと不充分な改善内容なのだが、それでさえ−99年度実施の予定が先送りにされている。
![[表1]各国の学級編制基準](37-1.gif) しかし、昨今、学校でのイジメの蔓延やイジメが原因の自殺の増加、不登校の激増、少年の凶悪な暴カ犯罪や女生徒の「性非行」の増加、「学級崩壊」にも至る「新しい荒れ」の発生・拡大など、小・中・高校の別を問わない学校内外の混迷と困難の増大が学校の内部努カの限界を超えるような程度に達するに及んで、テレビ番組や新聞の記事・論説・投書などにも、盛んに教育間題が取り上げられるようになり、ときには教育条件の改善の必要も説かれるようになっている。
しかし、昨今、学校でのイジメの蔓延やイジメが原因の自殺の増加、不登校の激増、少年の凶悪な暴カ犯罪や女生徒の「性非行」の増加、「学級崩壊」にも至る「新しい荒れ」の発生・拡大など、小・中・高校の別を問わない学校内外の混迷と困難の増大が学校の内部努カの限界を超えるような程度に達するに及んで、テレビ番組や新聞の記事・論説・投書などにも、盛んに教育間題が取り上げられるようになり、ときには教育条件の改善の必要も説かれるようになっている。
「経済の発展と引き換えに子どもたちの生活から奪ったものも多い。もうけた金の半分くらいは子どもの本当の教育のために返したらどうか…」(朝日新聞、98.6.8)「クラス定員を減らすには、先生の人件費などで大きな費用がかかるのは事実だ。(しかし)子どもたちが健やかに成長できるかどうかは、国の将来がかかった間題である。にもかかわらず政府は、銀行の救済などに何十兆円も投入しようとしている。歯がゆい」(朝日、98.4.5)。
将来構想検は、『中間まとめ』を見るかぎり、現に子どもと学校がかかえている問題を脇に置き、中央の方針に従って、「新しい多様化」をテコとした高校の統廃合・再編成にもっとも力を入れているようである。しかし、もし「子どもたちの健やかな成長は国の将来がかかった問題」という認識に異論がないのであれば、そして神奈川の高校教育の今後に対して基本的な責任を負うと考えるのであれば、子どもたちの成長・発達の危機の極まりつつある今日、高校間格差・受験競争の解消と並んでもっとも緊急に解決が求められている問題、教育条件の整備・充実、とくにその基礎的課題である学級定員・教職員定数の抜本的改善に向け、「国の動向など諸般の事情」を乗り越えて、真剣に精力的に取り組むべきではないか。
日本は後進国なのだ
[表1]は世界各国の学級編成の基準を示している。これによると、欧米では1学級20人から30人が主流である。一例として、日本と同じ第2次世界大戦の敗戦国:ドイツの場合を具体的に見てみよう。
| たとえば私が訪れたボンやフランクフルトや西べルリンの、小学校から高校まで一クラスは二十五人学級であった(西ドイツでは州により学校によりいくらかの相違があるが、傾向的には、ほぼ同じだという)。実際の子どもの数は十八からせいぜい二十三くらいまで。しかし、一人ひとりが個性的でのびのびとしているクラスのふんいきは、日本の四十人や五十人学級よりも、さらに大きなエネルギーであふれかえっている。管理せずに彼らを魅きつけるだけの力を持った教師でなければクラスをまとめていくことはできないという。 数学や英語の時間には、教師が二人になるから、一人一人の子どもの座席を巡回する教師は、個人教授と同じように、わからない子、質問のある子の横で、一対一の問答形式で子ども自身に解答をみつけさせている。わからないのは私という空気はまったくなくて、大いばりで手をあげて「わからない」と申し出る。やっと今日わからせても、翌日はまた「わからない」と手をあげる子が多いのだが、教師は辛抱づよく納得いくまで相手になっている。 (暉峻淑子『豊かさとは何か』岩波新書、1989年) |
また、アメリカでは、今年1月に、クリントン大統領が「教員10万人を新たに採用し、(小学)1年〜3年の学級親模を平均18人に縮小する」と議会で宣言している。
1991年に、日本でやっと40人学級の編成が完了したとき(45人から40人ヘの法改正そのものは80年度に行われたが、11年間実施をサボっていた)、欧米ではすでに30人の水準に達していた。しかし、我が国の後進性はその後も放置されたままである。ドイツと同様、焦土から復興に努めた日本国の経済力は今や世界第2位のGDPを誇るまでになった。しかし、その富は、それを営々として築き上げてきた国民全体の福祉の向上にも、新しい世代の教育にも、その価値にふさわしい比率で配分されてはいない。これは、日本の民主主義−制度と国民の意識−の未成熟の問題でもある。
![[図1]学力と学級規模の関係グラフ](37-2.gif) 小さな学級で大きな効果
小さな学級で大きな効果
ケニヤのナイロビのイギリス系小学校の女性教師は言う。「教育に責任を持てるのは25人までですね。それを超したら教育ではなくなる。管理になってしまいます」(朝日、98.4.5)。
小さな学級にはどんなメリットがあるのか。
アメリカでは学級規模と学習効果の研究がさかんで、コロラド大学のグラス、スミス両教授が発表した「グラス・スミス曲線」が有名だ。
[図1]は、1979年にそれまでの50年間に発表された学力と学級規模の関係に関する論文、約300を、メタ・アナリシスという推理統計学の分析法によって処理し、両者の相関関係を定式化したものだということである。
この曲線を見ると、40人から30人の間では学力は50点程度に停滞的であるが、30人をきるころからしだいに曲線は急勾配となり、20人では55点、15人では58点、10人では約65点、5人で約75点となった。きわめて単純な要素だけを取り上げたグラフで反論もあると言われるが、学級規模が小さくなると、学習効果が増すことは現場の経験によっても認められるところである。
![[図2]子ども1人当たりの教師の指導時間と学級規模の関係グラフ](37-3.gif) [図1]と関連して、[図2]の曲線にも注目したい。
[図1]と関連して、[図2]の曲線にも注目したい。
これは、教師の一日の授業時間=指導時間を200分とした場合の「子ども一人当たりの教師の指導時間」(Y)と学級規模(X)の関係を示したもので、その式はY=200/Xで、両方の図はほとんど相似形で一致する。学級規模が小さくなるにつれて、子ども一人当たりの教師の指導時間が増え、学力が向上するものと考えられる。
「学級規模が小さくなり、ー人の先生の教える子どもの数が少なくなるほど、授業内外での個別指導時間は増え、一斉授業にたいする子どもの理解度に応じたきめ細かい個別指導が可能となる。そうなれば、授業ヘの関心も高まり、“落ちこぼし"もなくなり、理解力のある子どもはさらに深い知識を学び、どの子の学力もさらに伸びるはずである」(三輪定宣「学級・学校規模と教育効果」『教育』90年11月号)。このことは、現場の小学校教員の経験からも裏付けられる。「25人の教室なら、子どもたち全員に目が届きやすい。一対一で子どもと向き合う時間も増やせる。35人を超えると、教壇から見て視野に入りにくい子が出る」(朝日、98.6.8)。小さな学級は、また、一斉授業でないかたちの学習もさせやすくなる。実験・実習・スポーツ実技や芸術などの指導の際も個別に時間がかけられるようになる。障害のある子や特別の問題をかかえた子などへの対応にも余裕がうまれる。子どもたちの人間関係や―人ひとりの個性の把握も比較的容易になる。
人間が精神的安定を保つには、各自一定の空間を確保することが通常必要で、逆に、閉塞状況での過密状態はそれだけでも心理的抑圧と暴発の要因になる。物理的空間的余裕は、心理的余裕の必要条件である。学級のダウン・サイジングによって、子どもどうしの接触の機会も増え、相互理解がすすみ、誤解・曲解・先入観・偏見などから生じる摩擦・対立も少なくなり、争いを暴力でなく言葉で解決することができるようになる下地がつくられる。また、クラス全体になごやかな雰囲気が醸しだされ、しばしばクラスの結束力も強くなる。
学級定員減は、教育条件の向上であるばかりでなく、いわゆる「過員」問題を発展的に解消する手だてにもなる。また、新たな教員需要(雇用)を産みだし、それによって、新採用の削減や停止によって世代バランスが崩れつつある高校教職員の平均年齢の上昇を緩和することもできる。
やる気になればできる
日本で学級規模を欧米並みに30人以下にすることは、けっして実現不可能な夢物語ではない。中学卒業生の数が滅少に転じて以来、たびたびその実現可能性が論じられてきている。夢物語どころか、子どもの数が幸か不幸かどんどん減っている現代は、大きな出費なしに学級規模の縮小を実現できる絶好期なのである。千葉大学の三輪定宣教授(教育行政学)は、つぎのような学級規模縮小の具体的な手順を提案している。(1)教育を国の最優先課題と位置づけ、行革などによる予算削減の対象とはしない。(2)チーム・ティーチング方式の導入というやり方ではなく、学級定員そのものの削滅をする。(3)現行の基準で少子化に合わせて教員定数を減らし続けるのをやめ、30人学級が可能になる教員数を維持する、など(朝日、98.6.8)。
今年4月、ひとつの象徴的な「事件」が報道された。長野県小海町の二つの小学校が、1学級の定員を40人とする国の規則ではきめ細かな教育ができないと、今年度から、19人と18人の構成の「小人数」学級を始めた。町が独自に予算を組み、町職員として教諭2人を補充した。父母たちの反応は上々であった。ところが、長野県教委から、国が定める「学級編成及び教職員定数の標準」に違反しており、そもそも学級編成は都道府県教委の権限である等という理由で、待ったがかかった。「教育の機会均等、公平性の観点から是認しがたい」という理由も付け加えられた。県が文部省にお伺いを立てたことは文部省財務課コメント(朝日、98.4.11)からもうかがえる。
小海町は強く反発したが、結局、学級を1つに組み直し、科目に応じてチーム・ティーチングの形をとるということで妥協させられた。このとき国が考えたのは恐らくこういうことだろう。1つ認めたら、全国に広がる。管理統制をゆるめたら国の権威がなし崩しにされる。一般化すれば予算も付けなければならなくなるだろう。しかし、教育などに予算を回したくはない。県に押さえ込ませよう。
この問題の抜本的解決は、三輪氏も指摘するように、次代を背負う子どもたちの教育を行政のプライオリティの最上位に置くかどうかの選択にかかっている。従来行政が常用してきた「財政上の理由」はもはや通用しない。銀行やゼネコンなど大企業の支援・救済には巨額の税金をつぎこんでも、子どもたちの教育には税金はつかえない、とは言わせまい。安保条約上の義務はないのに「思いやり」で在日米軍に多額の税金を提供し、その子女には施設・設備をはじめゆとりのある教育条件・環境を整備してやり、小人数クラス編成を保障してあげても、自国の子どもたちにはしない、とは言わせまい。
文部省も一枚岩ではないようだ。小海町の件では、「財政措置ができるなら、自治体独自の判断は認められる。当省はコメントする立場にない」というコメントがあった(朝日、98.4.11)。また、省内には、「学級人数の削減が可能になるように国民の合意を目指すべきだ」「地方分権の流れから、国は財政援助だけを行い、学級規模は各自治体に任せた方がいいのではないか」などの意見もあるという(朝日、98.6.8)。
「団塊の世代」の孫世代が学齢期に達する20l0年ごろ、再び児童数が増加に転じると予測されている。それ以前の減少期になんとしてでも学級規模の縮小を実現する必要がある。そのためには、ひろく強く世論に働きかけ、主権者の共同で教育を最優先課題とする政府・自治体をつくらねばならないだろう。