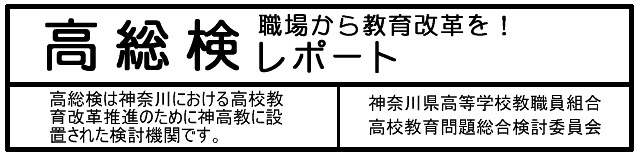
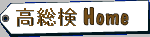
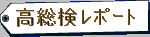
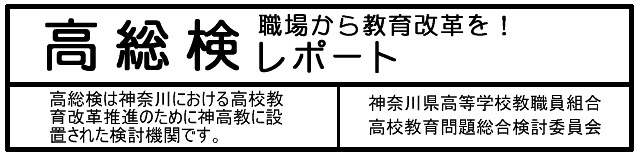
1.教員の専門性に対するさまざまな攻撃
学校教育法の定める教職の専門的自律性に根ざす教員の職務権限が、今まさにさまざまな攻撃にさらされている。
例えば、昨年12月7日付け『神奈川新聞』が1面トップで報じた、神奈川県教委が「指導力不足教員等」を見極めるための判定委員会を第三者機関として設置する要綱を策定したという記事。「授業を成立させられない」「生徒指導が適切でない」などの「問題教員」を学校当局者ではない第三者の目を通じて「客観的に判断」する必要があるという。「指導力不足教員等」のレッテルに「評価の客観性」というお墨付きを得て、該当者の排除に乗り出してきたとき、抵抗しにくくなることをむしろ恐れる。
また、昨年9月、「教職員人事制度研究会報告」(以下「報告」と略す)の形で示された勤評に代わる「新たな人事評価システム」の新年度からの導入。「目標管理手法」をうたいながら、実際は、学習指導、生活・進路指導、学校運営、特別活動の4つの評価項目で、能力・意欲・実績について5段階評価を下すというもの。本人の設定した目標とは関係なく「職務全般にわたる勤務状況」が評価対象とされる点は大きな矛盾だ。管理職による授業観察や同僚からの意見聴取、時には指導主事による参観などが行われれ、職務が日常的な監督と統制にさらされることは必至である。
1980年代にアメリカで教員の資質向上策として試みられた給与処遇と結び付けた信賞必罰的教員評価(メリットペイ)はそのほとんどが失敗したといわれる。「報告」には「人材育成及び能力開発を目指して」という副題が付けられているのは実に皮肉なことだ。かつて1990年代に「成果主義の人事評価制度」を鳴り物入りで導入した日本の某電気メーカーでは、社員の意欲を引き出すどころかマイナス評価を恐れて目先の目標ばかりにとらわれる「守りの姿勢」を強化する悪い結果を招き、ついに昨年末、1万人を越える大リストラの発表を余儀なくされた。県教委は少なくともこの事例に学んでほしい。
教育公務員特例法には、教員の研修は義務であり権利という定めがある。教員の「資質能力」を高めるためさまざまの研修の機会が保障されるべきは当然だが、昨今自主研修の権利は著しく制限されつつある。問題は、それに呼応する形で教員同士を競わせようとする策動が90年代末から目立ってきたことである。つまり、「資質能力」は、「育てるもの」ではなく「評価・選別の対象」というのが当局の考えなのだ。これによって職場はどう変わるのか?
2.教員の「資質・能力」の内容は何?
様々な教育課題の解決のために「教職員の力量」を高める必要性を否定するものはいない。しかし、「教職員の資質能力として必要なものは何か」という議論が未だ明確にされていないこの段階で「指導力不足教員」の判定や「新たな人事評価制度」の導入が行われればどうなるか。「指導力不足教員等の例」の中に「上司の指示や指導を無視し、勝手な行動をとる」がある。これは「資質・能力」として一括できる事柄だろうか。管理職による恣意的な判断を防止するに足る明確な判断規準の設置が前提だ。むしろ民間企業の例にあるように、管理職についての厳格な評価制度の導入の方こそ先行して行うべきなのである。このままでは教職の多面性が無視され、羅列的な「評価項目」にとらわれる傾向をつくり出す。そうなっては、「報告」の掲げる「学校教育が直面する困難な教育課題の解決をはかり教育効果の向上をめざす」という目的とはかけ離れた結果を招くだけであろう。少なくとも1987年の教育職員養成審議会の第1次答申のレベルは踏まえつつ議論する必要がある。教員の専門性についての議論はここから出発すべきである。
| 学校では、多様な資質能力を持つ個性豊かな人材によって構成される教員集団が連携・協働することにより、学校という組織全体として充実した教育活動を展開すべきものと考える。画一的な教員像を求めることは避け、生涯にわたり資質向上を図るという前提に立って、全教員に共通に求められる基礎的・基本的な資質能力を確保するとともに、さらに各人の得意分野づくりや個性の伸長を図ることが大切である。 (教育職員養成審議会・第1次答申 1987年) |
| 教育職は専門職として職務の遂行にあたって学問上の自由を享受すべきである。教師は生徒にもっとも適した教材および方法を判断するための格別の資格を認められた者であるから、承認された枠内で教育当局の援助を受けて教材の選択と採用、教科書の選択、教育方法の適用などについて不可欠な役割を与えられるべきである。 (ユネスコ・ILO「教員の地位に関する勧告」1966年) |
| 授業において、子どもはそれぞれに固有の生育史、家庭や地域の背景、独自の経験、学習歴をもって、固有名の子どもとして学んでいる。学級もまた個性をもった特定の集団である。教師は授業において、子どもたちの実態に即して、特定の教材を選ぶのである。このように、授業は固有名の子どもたちを対象に、特定の内容、教材に即して、特定の方法を選びつつ行われる活動であるが、教師自身もまた、特定の固有名の存在である。そのような関連において、実践は、基本的に個別の教師の判断と責任において行われるのである。 (稲垣忠彦「教師教育の課題」岩波講座・現代の教育6より) |
| 教員の活動は、相互に干渉せず、前例踏襲的・画一的になりがちであるといわれ、また、社会の変化に対応できない学校の閉鎖性も指摘されているところであり、「学校の常識は世間の非常識」と批判されるような状況があることも否定できない。・・・教員は、多くの民間企業や公務部門の職員と異なり、新採用時から上司の指導や指示をあまり受けず、ベテランの教員と同様に児童・生徒に接し、各自の発想や自主性に委ねられることの多い教育活動に従事しており、互いに切磋琢磨する契機が少ないことから、ともすると職場がマンネリ化しやすくなる。 (教職員人事制度研究会報告) |
7.「開かれた専門性」へ
これからの教職の「自律性」論議は、政府・文科省による権力的統制からいかにして教育課程編成権を守るかという方向だけに重点が置かれてはならない。教員を教職の「専門家」とし、教育活動の企画・実践・評価に第三者の介入を拒む発想は、教員が「真理の代理人」という特権的な地位にあるという錯覚に根ざしている。保護者を始めとする地域住民の様々なニーズをきちんと受け止める態勢を学校は未だ整えていないが、それは教員の誤った「専門性」認識と官僚的で形式的な学校運営によるものである。保護者が学校の教育活動に対して発言し、決定に参加する機会を保障する柔軟な形の教育実践こそ未来に求められる。ここに「開かれた専門性」を追求する根拠がある。
| 教師は学習を促進するだけではなく、市民性の育成と社会の統合を進め、好奇心、批判的思考、創造性、自発性、自己決定能力を発達させる。教師の役割はますます集団の中での学習のファシリテーター(支援促進者)となるだろう。・・・ 他の、情報を提供する機関や社会化機能を持つ機関が果たす役割が増大する中で、共通の教育目標に向かって様々なパートナーによって供される教育活動のコーディネーターとしての役割を果たす。 (教師の役割と地位に関するユネスコ勧告 1996年) |