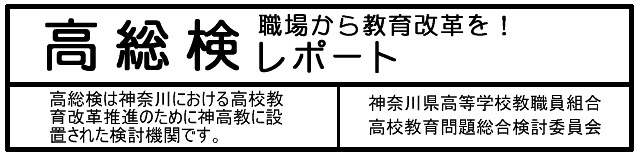
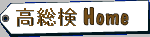
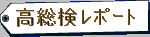
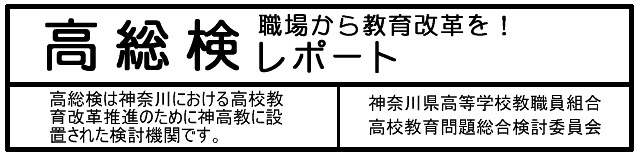
■授業評価の流行■
「授業評価」が話題になっている。東京都教育委員会が今年4月から「生徒による授業評価」を全都立高(207校1分校)で実施することを決めたというのだ。理由は、2001年に実施した「都民意識調査」で「生徒の能力に応じた授業を行っている」「生徒の興味関心に応じた授業を行っている」の項目への回答が低かったからだというもの。さらに、東京都の高校中途退学者の割合が全国平均より高いといった事情も理由にあげられてる。つまり、「授業がつまらない、勉強に意義が見出せない、と学校から離れていく生徒が多い」という判断が、「授業改善の一つの方策」として「授業評価」の導入を決定づけたというのだ。神奈川でもこの4月から全県立高校で「試行」に入る。もう少しすれば、「生徒による授業評価」は当たり前の現象になりそうだ。
大学での「授業評価」の取り組みは、数年前から盛んになっている。1991年の大学設置基準の大綱化で「自己点検・評価」が義務づけられたのを受けて「学生による授業評価」が導入された経緯がある。例えば、東海大学では93年から教育・研究活動をチェックする「自己評価」の一環として全学部で学生による授業評価が始り、現在、非常勤講師を含め授業を受け持つ教官一七〇〇名のうち、評価受け入れに同意した約八割が学生から授業評価を受けている。評価は春学期と秋学期の終わりの年二回、講義科目やゼミ、実習を五段階で評価するマークシート方式と、授業への要望などを記入する意見欄がある。結果は学内のイントラネットを通じて公開され、評価を受けた教官の九割以上が名前も明にしている。教官名の公表は「授業評価の効果を高め、学生が目履修科目を決める材料にもなる」としている。
それでは高校ではどうすべきか。
私たちはここで「評価」というものの本質的な意味を考えてみる必要がある。大学や高校で導入の動きか活発になりつつある「授業評価」を、単なる「流行現象」に終わらせないように。少なくとも私たちの構想する「教育改革」につながる方向で活用できるように考えたい。インターネットで試しに「授業評価」と検索をかけるとわかる通り、今や流行語の感のあるこの用語だが、中身をみるとほとんどがアンケート結果をただ羅列したものがほとんどである。plan−do−seeのプロセスの中で、「授業評価」は”see”に当たるわけだが、もう一度それが教育活動の中に生かされなければ意味はない。「授業評価」は、いわば「スタート」に過ぎない。要は「どのように授業改革につなげていくか」ということだ。
■東京都の授業評価■
先行している東京都ではどのようなことになっているか。東京都の「教育改革」の強引さは色々な場面で論議を呼んでいるが、都教委の示している「授業評価」の「評価項目例」を参考にしてみたい。
○先生の説明はわかりやすいですか。
○黒板の内容は整理されていますか。
○熱心に教えてくれますか。
○授業は楽しかったですか。
また、先行実施しているいくつかの高校の「質問例」には「チョークの色の使い方はどうでしたか」「講義にユーモアはありましたか」などとある。こうしたアンケート調査を年3回実施して通信簿さながらに観点別に5〜3段階で生徒に評価してもらう。「数字を示さないと教師の能力を十分に引き出せない」との考えに基づいて「力量」を数値化するというのが東京都の方針だ。
まず、どのような「質問項目」を設定するかは大きな問題だ。「アンケート調査」が調査対象である「生徒の意識」を規定していく危険がある。アンケート項目に並べられた項目が、あたかも「理想的な教師像」であるかのように機能してしまうのだ。当然、評価を受ける教員自身も「理想的な教師」を演じるよう誘導される。「質問項目」を全県一律の形にするのは極めて危険な行為であることを銘記せねばならない。「ものさし」であるべき「授業評価」が「教育のあり方」を規定してしまうことは避けるべきである。東京都の例では「特定の授業のあり方」を誘導するような傾向が見て取れる。その傾向とは、生徒をお客さんの立場に置いている、ということだ。
「新採用教員の時代に授業アンケートを取ろうとしたら、先輩教員にたしなめられた」という話を聞いた。「授業はそもそも生徒の反応を十分に観察しながら行うべきもので、1年間の授業の終わりに改めて生徒に意見を聞くなどナンセンス。そんなことをするのは生徒からいい評価をもらって一人悦に入りたいからだ」ということだろう。改めて「授業評価」と断らなくても、生徒の理解度を常にモニターしながら、私たちは授業を続けているはずだ。そもそも生徒のとの相互的なミュニケーションなしに「授業」は成立しない。
アンケートが生徒を「観客」のような立場に押し込めるような作用をもってはならない。
むしろ、生徒を教育活動における「一方の当事者」として位置づけることが必要であることを、この際確認しておこう。
■古くて新しい問題■
私たちが「授業評価」を論じる際に有力な手掛かりを与えるのは次の文章である。
「本来、教育課程の計画や展開について、示唆を与えてくれている学習指導要領や、その他の文書は、あくまで実施のための手引書であって、それをどのように生かしていくかは教育を実践する教師ひとりひとりの責任にかかっている。その意味で、みずから実施した活動について、絶えずあらゆる機会においてそれを検討し、評価し、これに改善を加えていく責任が、とりわけ個々の教師に課せられている」
教育実践の一連の流れにおける「主体」としての教員の責任に関して明確な意識をもって書かれたこの文は、1951年、当時の文部省によって「試案」として出されていた「学習指導要領」の一節である。私たちは50年以上前に書かれた文章が雄弁に物語る事実を再確認しなければなるまい。「教育評価とは何か」。これは古くて新しい問題なのである。「本来、教育評価というものは、教師にとっては授業効果の測定、生徒にとっては自己の学習内容の到達度の自己評価としてありうるものである。このばあいは両社の評価が必ずしも一致するのではなく、教師の方の評価が一方的に正しいともいいきれない。(中略)今日の学校における教育評価は、教師にとって一方的に行われている。したがってそれは必然的に教師による生徒の到達度の判定のみに偏ってしまう。その極端な形態がいわゆる偏差値であって、それは生徒相互の相対的関係しか表示しえない。教育内容がまったく捨象されてしまうのが最大の特色である。教師の考え方への評価もほとんどまったく免責される仕組みになっている。これもまたきわめて一方的とはいえないだろうか。(中略)教師はそうした偏った「評価」を問いなおすべきだろう。」
■教育評価に責任をもつのは誰か■
今こそ「教育評価とは何か」という「古くて新しい問題」に立ち返るときだ。それはあくまで「教育のための評価」でなければならない。言い換えれば「教育活動全体の評価」すなわち「一定の人間に対して教育を行い、その結果を点検するときに行われる評価」なのであって、「選別のための評価」と厳密に区別されなければならない。
日本の教育の世界では、従来「評価」はもっぱら「生徒を選別するための手段」として行われる傾向が強かった。「教師」は「評価をする側」ではあっても「評価される側」ではない、という特権的な地位に身を置いてきた。現在進行中の動きは、生徒や学生が「教師を評価する」ということであり、「教師」をこれまでの特権的な地位から転落させることだ。これはある意味当然のことである。「授業評価の導入」に対して私たちが抵抗でないのは、生徒や学生が「評価の対象」の側に一方的に固定されてきたことの不当性を認識するからである。
「生徒による授業評価」を考える際に踏まえるべき原則は次の項目に尽くされているだろう。
■生徒による授業評価の「もう一つの意味」■
「教育評価」を考えることは、教育の場における教員と生徒の関係を考えることでなければならないことはすでに述べた。ここで、もう一つのことに触れておかなければならない。それは、いわば学校という場における教員と生徒の「権力関係」ということである。
「子どもの権利条約」は、権利実現の過程に子ども自身が「参加すること」でようやく実現されることを強調している。すねわち、「子ども」を「権利主体」と位置づけることが要請されているということだ。「子どもの学校参加」の定義はとりあえず「子どもが必要な情報を得ることを前提としながら、学校の管理運営の過程、さらにいうならば学校の意思決定の過程に参加すること」(藤田昌士『生活指導』1995年2月号)としよう。その意義は、子どもは学校を構成する一方の権力の主体である、ということだ。
汐見稔彦のいう「教えることの罪深さ」(p,90) は、教育論の視点から教育目標設定を「教師が預かる」という「代行」説を批判して「参加」説に立った発言である。しかし、私たちは一歩進めて「権力論」として、教育目標が適切かどうか判断する「一方の主体としての生徒」という視点に立つべきである。すなわち「参加」を、教員と生徒が協議して決定する「共同決定」の意味に解することである。
したがって、最初から「とりあえず生徒の声を聞いておこう」という程度に「生徒による授業評価」を位置づけるのは間違いということだ。もちろん職場によって生徒の現実には様々な差異があるので、「参加」の形態は一律ではありえない。真の意味での「生徒参加」は「参加」を通じて権利行使能力の育成の結果実現されることも事実だ。それぞれの教育現場にふさわしい「共同決定のあり方」を生徒との話し合いによって築き上げていく。
そのプロセスはけっして気楽なものではない。しかし、生徒にとっては戦後50年以上に渡って民主主義の辺境であった「学校」という場を、「子どもの権利条約」の方向に一歩前進させるきっかけとして「生徒による授業評価」の導入の意義があると思えば、私たちにとっても努力のし甲斐があると言うべきだろう。