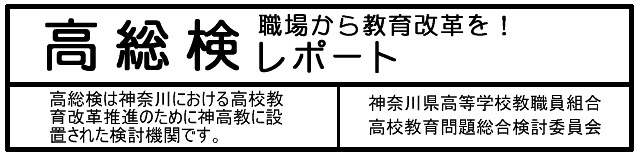
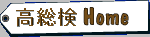

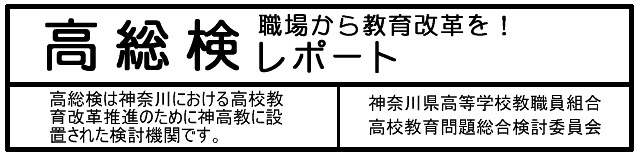
「生徒による授業評価」の来年4月からの県下公立高校での一斉実施に備えて、各職場では実施方法についての論議が進んでいるだろうか。「生徒による授業評価」を「子どもの権利条約」と関連づける視点については3月の『高総検レポート№66』で述べたが、今回は憲法の「学習権」、教育基本法第10条に戻って考えてみたい。
さて、県下の高校現場における目下の関心事は「生徒による授業評価」よりは「シラバス」の方であろう。高校教育課教育指導担当が今年4月作成した「これからの評価のあり方」によれば、年度始めの4月に「各教科・科目の最初の授業において、各担当者がシラバスを生徒に提示し、年間の学習計画を説明する」とある。それを前提として年2回の生徒による授業評価を実施し、授業評価をもとにした研究授業や校内研修会等がほとんど義務づけられている。シラバスという法的根拠のないものが有無を言わせず高校現場に降りてくるのは「生徒による授業評価」のせいだと感じられても無理はない。
ここではあらためてシラバスと教育課程編成の関係について考えてみる。
北海道学力テスト事件と「学習状況調査」
教育課程編成への国家権力の介入をめぐって戦後教育の歴史における大きな争点となったものにいわゆる「学力テスト」問題がある。日教組を中心にして全国的な規模での反対運動が展開される中「事件」が発生した。1960年代当時の文部省が全国の国公私立の中学2、3年生全員を対象として「学習指導要領の徹底度を調査する」という目的で実施した「学力調査」に対して、北海道で行われた中止要請運動が公務執行妨害に問われたのである。一審の旭川地裁、控訴審の札幌高裁判決は、学力調査を教育基本法第10条1項目(=教育行政の「不当な支配」)に違反するとして公務執行妨害罪の成立を否定して注目された。
判決は、この学力テストを単なる行政調査と判断せず、結果を生徒指導要録に記載しなければならないため日常の学校教育活動に及ぼす実質的影響が大きいと判断する。「日常の教育活動を、調査の実質的な主体であり、問題作製者である文部省の学習指導要領等に盛られた方針に沿って行うという空気を生じ、教員の自由な創意と工夫とによる教育活動が妨げられる危険がある」と学力テストの本質を認定した。また、教育行政機関の教育内容への関与の程度は、「教育機関の種類等に応じた大綱的基準の定立のほかは、法的拘束力を伴わない指導・助言・援助を与えるにとどまる」とした。
今私たちはここで「学力テスト」の代わりに「シラバス」と代入して判決を読んでみよう。二つの問題が余りに共通していることに驚くのではないか。また、今年11月に実施が予定されている神奈川県の「学習状況調査」もまったく同様の問題をもつことは明らかである。詰め込み方の教育からの脱却をめざす新学習指導要領の精神に反して特定の内容だけを取り出して調査の対象とし、各学校が努力して進めている教育課程の多様化にブレーキをかけものだからである。
旭川学テ最高裁判決と「教室内の民主化」
一方、旭川学テ最高裁判決は「国民の教育権論」「国家の教育権論」の両方を極論として採用せず、両者の折衷的見解を示すと共に学テを適法としたものであるので、「国家の広範な教育への介入権」を認めた判決と解されている。しかし、ここではこの判決の教育人権宣言的な要素に着目したい。判決の憲法第26条「教育を受ける権利」についての記述にはこうある。「子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習する権利に対応し、その充足をはかりうる立場にあるものの責務に属するものととらえられているのである。」また、国家の教育内容決定権については、「必要かつ相当と認められる範囲において」認めつつ、「できるだけ抑制的であることが要請される」とともに「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を強制するようなことは、憲法26条、13条の規定からも許されない」とある。
旭川学テ最高裁判決は、明確な形ではないけれども、二つの教育権論に対して「教育をうける側の権利」すなわち「子どもの学習権の保障」の宣言を行ったと見るべきだろう。問われているのは「国家か国民(教員)か」の対立ではなく、「教員と児童・生徒」の関係なのだ。教育の民主化は「教室の中」にも確立されなければならないからである。
「教育を受ける権利の保障」と「教育権の独立」
「教育を受ける者の権利」(学習権)に奉仕するために、学校教育の場で子どもや青年の学習権の保障に直接的具体的にかかわっている教師の教育権の独立をいかにして保障するか。この問題は戦後の教育政策が憲法・教育基本法に示された原則に反して、教育における国民と教師の権利を抑制しようとしたときから始まった。具体的には、勤評、学力テスト、教科書検定において争点となる。
教育基本法第10条1項の「教育権の独立保障」は、教育は子ども一人一人の成長発達をめざす営みであるという大前提の認識と教育内容の決定については戦前の反省を踏まえて政治的な支配からの独立性をいかにして確保するかという問題意識から生まれたものである。そこから行政権力からの独立を可能にするために要請されるのが「教師の専門的な自立性」である。私たちは今教育基本法第10条の以下の条文を改めて重く受け止めるべきではなかろうか。「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」
それでは「直接に責任を負う」ためにはどうすればいいか。そこで考えなければならないのは「開かれた学校づくり」の意味である。
1980年代からの「開かれた学校づくり」
最近では「開かれた学校づくり」は行政側の用語である感があるが、この試みの発端は1970年代に教職員組合を中心として学校運営の民主化のための具体的な提起として始まった運動であることを確認したい。北海道・宗谷の教育運動では次のような文書の成立があった。「・・・どの子にも基礎学力をしっかりつけさせること、非行をなくし自主的な規律や市民道徳を身につけさせること、ゆたかな情操と体力を養うこと、希望と適性にもとづく進路選択への援助など切実な教育の課題−父母の期待−にこたえるためには、各学校の校長をはじめすべての教職員はもとより、父母・教育行政・教育関係者が憲法と教育基本法の理念を基盤にそれぞれの責務を自覚し相互に協力することが重要です。」しかし、こうした提起に対する当時の文部省・県教委の態度は否定的で頑であった。
また、1990年代に長野県、千葉県、高地県で始まった生徒・教員・父母による三者協議会(一部は地域住民を加えた学校協議会)の実践は、学校運営の民主化を生徒を含める形で実現しようとしたものである。千葉県立小金高校の例を見ると、卒業式での「国旗」「国歌」の義務づけに対する生徒の反発から始まった三者の話し合いが、保護者側の提案を契機に、相互の恒常的な意見交換と相互理解のための場に発展したものである。しかし、こうした民主的な学校運営は県教委と校長の圧力による妨害に晒されることになる。2001年2月21日の「弁護士21人を含む市民有志26人からの要望書」によれば事情はこうだ。「千葉県立小金高等学校・同東葛高等学校・同国府台高等学校の3校では、子供の権利条約施行以前から、生徒と教師と保護者が対等な関係で話し合いによって学校運営をする民主的なルールと校風が育まれ、卒業式等の学校行事についても、生徒・生徒会の意向を職員会議が尊重し、生徒主体の卒業式が行われたと聞いております。これは、子供の権利条約の保障する意思表明権や学校運営への参加権を認める素晴らしい伝統であり、私達も高い評価と関心をもつところです。」
今日の学校運営に父母・生徒を参加させるべきであるという考え方が有力になってきた背景には、第一に「子どもの権利条約」に「意見表明権」明確に示されたことによって生徒の意見を尊重していこうという気運が醸成されたことがある。また同時に、学校をめぐる様々な教育問題が深刻化し危機的状況を迎える中で、その打開策として「参加」型方式が有効であることが再認識されたことがある。「開かれた学校づくり」は「教室内の民主化」という意味をもつこと再認識すべきだろう。
1998年中教審答申の「裏切り」
草の根的な「開かれた学校づくり」運動が一定の盛り上がりを見せる中で、行政側の真摯な対応が当然期待される。しかし1998年の中教審答申は心ある多くの人々の期待を完全に裏切るものでしかなかった。こうして誕生したのが現在の「学校評議員制度」であり、それが「校長の応援団」として校長の学校での管理運営権限の強化を狙うものでしかないことは周知の通りである。この制度は欧米で一般的となっている保護者・住民との共同決定システムとは全く異質な代物である。
一連の教育における制度改革は何を意図しているのか。日本社会においてほとんどの組織がピラミッド型であったのに対して、戦後60年近くを通じて学校だけがその例外の地位を守ってきたことに関係がある。学校がピラミッド型組織になることを阻んだのは戦前の国家主義教育に対する反省と「横の組織」や「合議制」の方が学校現場の特殊性に合致していたからでもある。ここ数年「横の組織」原理に手をつけようとする動きが巻き起こっているのだ。
現在進行中の「学校改革」が従来とは反対の組織原理=「縦の組織」を持ち込もうとしていることは明白である。東京都がその先行例で、「人事考課制度」のもと主幹を配置し、校長―教頭―主幹―主任の命令系統を整備しようする意図は、ピラミッド型組織を教育現場に根を下ろさせようということに他ならない。この仕組みが実現すると次のような光景が展開される。
「教員はまず教科の年間授業計画(シラバス)を作成するため、学校目標及び目標の具体的な手立てに沿う指導計画の調整と観点別評価規準策定を同じ教科担当と行い、指導項目と指導内容を決めたシラバスを作成する。教科主任が教科のシラバスを点検して、学年担当主幹がチェックして、教頭に提出する。教頭段階で書き直しを求められたり、さらに校長に提出し、校長から呼び出され、訂正を求められることもある。」(『ねざす№33』所収、池田弘氏論文p.79-80)
生徒参加のプロセス
藤田昌士氏は、生徒参加を「評価」段階における生徒参加と「計画」段階における生徒参加の2種類に区別している。
「評価」段階のおける生徒参加は、現在日本全国で進められようとしている「生徒による授業評価」が該当する。教える者と学ぶ者の自己反省のための重要な手段を提供するものである。教師に対しては教育活動の改善に役立ち、生徒に対しては授業に対するよりよい動機づけとなる。
一方、「計画」段階における生徒参加は、ドイツで制度化されている「授業計画フォーラム」が該当し、「定期的に、あるいは学級や学習グループの求めに基づいて実施され」「そこでは、授業に関する教師の説明と授業の計画に対する生徒の提案が審議される。」 千葉県立小金高校と高知県立伊野商業高校の例は「計画」の段階における生徒参加を実現している。両校の場合は、当初は当面の需要への要望を出し合う「評価」段階からスタートして「計画」段階に進んだ。小金高校では、生徒会による授業アンケート実施とそれに基づくホームルームや三者会議(教員・生徒・父母)での討論を経て教師に対して要望を提出する。また、「高校生に求められる学力とは何か」などを問う講演会とパネルディスカッションなどを開催し、「総合的な学習の時間」の内容を三者検討委員会の活動の対象にしている。
「開かれたシラバス」と「話し合い」
「評価」という言葉を現在神奈川で話題になっているような狭い意味での「授業アンケート」に限定して考えるべきではない。むしろ生徒のトータルな学習活動のPDCAサイクルにキチンと位置づけ、重要なプロセスとして捉えるべきである。そうすれば、「シラバス」を提示して年間授業計画を生徒に説明する中で、出された生徒の要望を早速反映させなければならない。1学期末、2学期末のアンケート実施時についても同様である。
この場合、「生徒による授業評価」は「アンケート」の形のみで終了させるべきではない。生徒の生の声を教員側が謙虚に受け止めるためには、むしろ「話し合い」を実施した方がよい。そして、「話し合い」は個別の授業担当者との間の話し合いよりもむしろ、三者協議会などの場での責任のある場での話し合いの方が相応しい。授業のあり方だけでなく、行事や学校運営全般を対象とした話し合いを公開討論会の形でもつべきである。教員と生徒が対等の立場で率直な意見交換する方法・システムを整備することによって、生徒の側に学習主体としての自覚が生まれ、自分の発言に責任をもつようになる。
シラバスの「授業マニュアル」化に反対しよう
生徒の学校参加は「計画」段階における生徒参加に向けて取り組まれるべきである。したがって、現在神奈川で進行しつつあるような、学習指導要領をそのまま写し取ったような授業マニュアル的シラバスに反対すべきである。むしろシラバスは生徒の授業参加、授業計画への参加を促すための手段であるべきだ。生徒が「学習の主体」になるとはこういうことである。
県教委作成の「生徒による授業評価試行実施要領」の「8 生徒による授業評価のまとめの活用」にある「校長は、生徒による授業評価のまとめを、次年度の生徒による授業評価の取組に反映させるほか、当該校の学校目標、評価基準・シラバスの内容等についても併せて見直しを行うなど、生徒による授業評価のまとめを活用し、確かな学力の向上をめざして、授業の質の向上に努めるものとする」を字義どおり実施する。むしろ次年度と言わず、生徒との話し合いの結果を出来るだけ速やかに授業内容に反映させる。シラバスは単なる計画書ではない。生きて働く授業の道標である。
したがって「シラバス」はけっして硬直したものであってはならず、学習主体(=生徒)に開かれているべきである。生徒にとって「確かな学力の向上をめざす」には、生徒自らが学習主体としての強い動機づけを伴っていることが条件となる。シラバスを学習指導要領で拘束することは、生徒を学習主体の地位から転落させることだ。
教育課程編成において学習指導要領による拘束を所与のものとする考えに陥ってはならない。小金高校の三者会議発足の経緯には、入学式・卒業式での「国旗・国歌」の義務づけ問題があった。生徒を教育課程編成に参加させるという視点は、学習指導要領による国の規制を跳ね返す契機となる可能性がある。「教室内の民主化」は私たちの最後の砦なのだ。