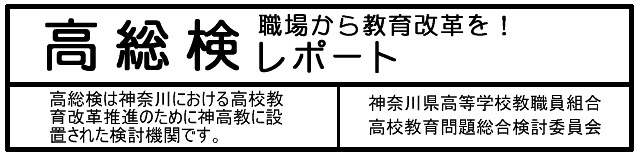
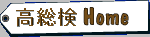

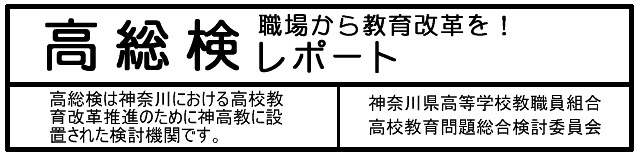
「観点別評価」の実施を目前に控え各学校現場では混乱と不安が広がっている。しかし、いまだこの施策をめぐる議論が整理されず、これに潜む本質的な意味と、もたらされるであろう結果があまりに曖昧な捕らえ方しかされてはいないのではないだろうか。
「観点別評価」には賛成だが拙速な導入反対、から、教育上本質的問題があるという論まで、さまざまである。そして今のところ、「拙速な導入反対」でかろうじての一致を見ているに過ぎない。
しかしたとえ導入不可避となった今日でも、この「観点別評価」の問題性を追及すべき議論はもっと大々的に展開されるべきだし、その営みを通して私たちが目指すべき学力とは何なのかが明確に理論化され、現場で働く私たちの共通認識として広められることが必要なはずである。
その本質的危険性と欺瞞性が、理論的に整理されているかいないかは、実施せざるを得ない現状においても私たちが「観点別評価導入」の圧力にどういう態度で臨むべきなのかの視座を与えるし、将来の「見直し」という契機に備えることにもなるだろう。
以下に、展開する論点はそのための議論の一材料となればと思う。
0. 「観点別評価」と「新しい学力観」の関係
県教委による学習会や、解説用冊子の中で主張している「観点別評価」導入の論拠を見てみよう。まず何故やらなければならないのか、それは
| 「…従来のような知識を教え込むような授業のあり方を改め、子供たちが自分で考え、自分の考えを持ち、それを自分の言葉で表現することが出来るような力の育成を重視した指導をいっそう進めていく必要があり…」(『目標に準拠した評価・観点別評価の手引き』/高校教育課) |
というわけである。そして「授業のあり方を改める」必要があるとする根拠は、
| 「学習指導要領の改訂で、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資質や能力も学力の基本ととらえる新しい学力観が示されていたが依然として知識や技能を重視する授業観が見られる傾向があった。そこで…」 |
というわけである。そしてこの『学習指導要領』の文言は『教育課程審議会答申』を論拠(というか引用)としている。
そこには、おおむねつぎの4点が挙げられている。
|
論理的筋道でいえば、「観点別評価」(評価を変える)⇒ 授業と学校のあり方の変換が起こり ⇒ 学力観が改まる ⇒ 「新しい学力観」の完成ということで「新学力観」と「観点別評価」は互いに双対の関係にある。
幾つかの疑問が湧いてくる。おもに以下の2つを上げる。
① まず「新しい学力観」とは何か?
② 通信簿を変えれば「授業のあり方」は正しい方向に変るのか?
「新しい学力観」が、「知識」偏重、自分で考える力の不足の議論から来ているのだとしても、はたしてただ「学力観」を変える事ですむ話なのか? またここで言われている「知識」とは何なのか? 「評価」のもつ機能と役割を授業改善や、学習活動の改善の手段としながらも、つまるところ通知表を複雑にしろといっている。この2者にはあまりにギャップがある。以下では、この点を明らかにしていきたい。
1. 「新しい学力観」はどこから来たのか?
新自由主義が声高に叫ばれはじめる90年と前後して、それまで「基礎学力の充実」「学力保障」「落ちこぼしの教育」などといった学力問題に対する投げかけは、めっきり聞こえなくなり、その代わりに言われだしたのが「個性尊重」「教育の多様化」「心の教育」そして「生きる力の育成」などだった。では、低学力問題は解決されたのかというと、その気配すら無く、むしろ当時から現在に至るまで、「落ちこぼれ」といわれる層の子供たちは増え続け、格差は深刻になるばかりである。にもかかわらず数年前から今日に至るまで「学力」が問題視されるとしても、それは「新しい学力観」という論点の中に押し込められてきているように見える。かつての「学力」は「知識・理解」のことばかり言っていたから、こんどは「意欲・関心・態度」を中軸に据えた「新しい学力観」をつくろうというのである。
92年に月1の学校週五日制が導入され、小中学校では年間にして240日程度から230日程度、授業時間にして年間約35~40時間が減らされた。
95年の月2の週5日制導入では、さらに減らされ6日制の時と比べて年間70時間~80時間も減らされたことになる。しかしその一方で、『学習指導要領』で「取り扱われねばなない」とされた教育内容は6日制の時と同じであったから、授業進度は格段に速くなった。
そして、02年度に完全学校5日制が導入され今度は教育内容の「厳選」がはじまり、その削減率は約20~30%といわれている。当然著しい学力低下が明らかになった。しかし、これをみた中教審委員達の頭に浮かんだのは「学力観を転換させる」「評価の考え方を変える」ということだった。「知識」の量ではなく、全人的力である「生きる力」を学力としよう、そうすればかつてのような学力低下を心配する必要はなくなる。
このように書くと「ちょっと待ってくれ」と、「新しい学力観」の支持者達は言うかもしれない。「これまでのような、記憶された知識の多少だけで、人間性までをも計るような『学力』のあり方が、社会通念とされていてよいのか?」 と。たしかに、どこかで用意された「知識」をただ暗記して、何かに盲従していくようなことが奨励される「学力」は困る。憲法や教育基本法で定義された、民主主義社会の主権者として労働していくためには、それこそ、目の前にある知識を批判的に解釈し、自分で問題を見つけ、計画を立てて学び続ける能力が無ければならない。それには学力観の転換が図られなければならないだろう。しかし、だからといって「新しい学力観」で頭の切り替えをすることでそれは済むのだろうか。あまりにも漠然とした「全人的な力」であるとか「生きる力」であるといって「学力」を無限定に拡大させていくことでいいのだろうか。
95年に日経連が『新時代の日本的経営』を発表した。その中では、これからの期待されるべき雇用形態として「長期蓄積能力活用型」(エリート)、「高度専門能力活用型」(技術者)、「雇用柔軟型」(不安定雇用のその他大勢)の三つが上げられ、労働市場、労働法、労働政策をそれに見合うように「改革」しなければならないと言われていた。そして労働者を生産する学校もこれに合うように再編されなければ成らないと宣託をされた。
02年には「ゆとり教育」の扇動者であった三浦朱門1の有名な発言がある。
「落ちこぼれをなくすのに使ってきた労力と時間を『さまざまな才能をのばす』方に振り向ける」(2002年3月11日AERA)。
「限りなく出来ない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養っておいてもらえばいいんです」(『機会不平等』/斉藤貴男著)。
これらのことをあわせて思い起こすと、「ゆとり教育」「新しい学力観」「観点別評価」と連なる一連の言葉がどこから来たかが見えてくるのではないだろうか。
2. 「新しい学力観」とは何か?
* 出発点じたいが間違っている
「新しい学力観」では「知識」がばらばらな単なる情報の集まりであるかのごときに語られている。たしかに試験で点を取るという目的に特化した断片的な情報集積物を頭に詰め込むことが、「知識」を得ることと勘違いされている社会的風潮があるが、それは主に、学校暦2偏重と、受験競争の帰結であろう。本来「知識」という語が指すものは、客観的に妥当だと判断しうる情報を有効な原則に従って分類し、体系付けたものをさすのであって、クイズ番組的な「雑学」を指すのではない。したがって「知識」の中には「思考」も「判断」も「技能」も「表現」も包含する概念であるはずである。しかし、「新学力観」と「観点別評価」では、乱暴にもこれらを同列にして個別に評価しろというのである。しかもその理由がこれまでの評価が「知識」偏重であったからというのである。議論の出発自体に言葉のすり替えによるごまかしがある。
* 学校の本来果たすべき役割との矛盾
安直に「知識偏重」を否定的媒介として、「生きる力」という曖昧な朦朧観念で「学力」を定義することはその概念自体を霧散させることになるのではないか? そしてその「学力」を基本軸とした教育論は学校教育の守備範囲の曖昧化=無限定化をもたらし、延いては、学校教育の無責任化・空洞化、教育の偽装工事につながる。
また、「観点別評価」によって「知識」以外の「学力」が選別材料とされる一方で受験競争と学校暦社会の加速は進んでいる。「知識」を持つ階層と持たざる階層との二分化をよりいっそう加速している。
そしてこの階層化は「多様化」や「特色」や「個性尊重」とすり替えられている。1996年12月の行政改革推進委員会報告は次のように推奨する。「学校間に多様性が存在することが〔格差〕であるならば、今後はこのような〔格差〕を義務教育制度の中でも積極的に肯定していく必要がある」と。
もちろん、このように「多様化」「特色」「個性尊重」路線導入には、階層化の意図があるにせよ、この矛盾を逆手に、学習指導要領に開いた風穴として、環境教育や開発教育、平和教育などの教育実践の優れた積み重ねもある。このような取り組みは、教育現場にいる私たちこそが取りうる抵抗の1つとして追求されねばならない。
だからこそ、本来の学校教育の使命は、社会の階層化を願う者たちの言う「個性尊重」や「生きる力」などではないことも忘れられてはならない。飽く迄本当の意味での知識を伝えることではないだろうか? 知識を伝えることを通して、人格の完成の資することではないだろうか? 今日の複雑な社会にあっても「平和的な国家及び社会の形成者」であり、「主権の存する国民」になるために必要な一定水準の知識。いわば民主主義社会のインフラ3としての知識の伝達がまず第一義に来なければならないはずである。そしてそれを可能足らしめる物理的諸条件の整備が行政の使命なのであって、いたずらに学力観をいじくることではない。
3. 「評価」と「評定」の欺瞞性
総合教育センターが作った観点別評価の解説資料『高等学校における観点別学習状況の評価』では、「評価の機能と役割」として、生徒、教員、学校それぞれに対して次のように分析している。
| 生徒にとっては…①自らの学習活動の反省と改善。②生き方の確立や進路選択のため。 教師にとっては…①授業計画の確認・調整。②生徒の把握と対策のため。③指導法の検討と改善。 学校にとっては…教育課程の改善と見直しのため。 |
どれももっともすぎて、何も言ってないに等しいほどである。ここに書いてあることは「評価」の目指すべき理想としては共有できるが、今日的学校の中で行われている(行わざるを得ない)「評価」の分析だとすれば、欺瞞である。ここには「評価」の「教育的機能」と呼ぶべき側面のみが強調されているにすぎない。しかし日常私たちが行っている「評価」には「教育的機能」とは矛盾するもう1つの側面が在る。それは「評価」の「統制的機能」である。
どの学校で、どのような生活をし、どのような成績をとってきたかは、将来何らかの形で働いていく子供たちの経済的・社会的地位を、無慈悲に決定していく。今日においてなお学校はそういう社会的関係の中に結び付けられ、決して社会とは無縁の理想郷の中にあるのではない。そして学校のもつ選別機能の中で「評価」が果たす役割は大きい。だからこそ生徒は「評価」に恐れを抱き、「単位を落とすぞ!」という脅しが効くのである。従って、「統制的機能」は点数付けをし、生徒集合の中に順序関係を持ち込むことを通じて、実現されている。
このことを、県教委は当然わかっている。だからこそ、高校教育課の『目標に準拠した評価・観点別評価の手引き』にも、教育センターの『高等学校における観点別学習状況の評価』にも、わざわざ「評価」と「評定4」を分けている。つまり、「評価」については、上述した「教育的機能」のみを強調し、「評定」については「点数や記号を付与すること」であると新たに定義しなおしている。そして「評価というと往々にして学期末や学年末に成績をつけることだと思われている面もあり、評定と評価を同じ概念でとらえないことも押さえておきたい」と峻別し、「点数付け」=「選別」と「評価」は違うんだということを印象付けて、「観点別評価」には「教育的機能」のみ説明し、これと矛盾する「統制的機能」については何の言及もしないことで、これを覆いかくしている。この現実を無視した論が、現実に適用するための「手引き」とまで銘打ってあるところに、まさに欺瞞が存在する。
4. 「関心・意欲・態度」の数値化は可能か?
この「観点別評価」の実践上の困難には、作業量の膨大化による矛盾と特に「意欲・関心・態度」という生徒の内心にかかわる、目に見えない対象を客観的に数値化するという矛盾の二つがある。
前者の矛盾は、「観点別評価」の大きな目的のひとつとして掲げられている「指導と評価の一体化」の中に現れている。「指導と評価の一体化」とは、「評価活動を評価のための評価に終わらせるのではなく、指導の改善に生かすことによって、指導の質を高めること」であると言うのだが、現実には著しい多忙化の中でそれが不可能なのは明らかである。かりに今回の「観点別評価」が指導改善に何らかのアイデアを提供するとしても、改善を実施するための時間は残されていない。指導の改善、授業の改善はその実践を計画し実行するだけの十分な時間と余裕が無ければ出来ないのに、この評価方法はその時間を作らせないためにあるかのように見える。例えば、12科目の授業の通知表を作る場合、生徒1人当たり12×4+1=49個のA、B、Cなどの記号を羅列する。これが40人学級なら、49×40=1960個の記号を通知表に記載する。このほかに評定や所見や出欠の記録を記載する。この膨大な量の記号を確認するだけでかなりの神経をすり減らさねばならないだろうし、「教師の主観的評価に陥らないよう」説明するための膨大な「観点別評価」のための資料を用意しなければならないのである。
後者についての議論は、「知識・理解」をある教科書を丸暗記させて、テストでその記憶量を測る通俗的な解釈に言い換えることではじまっている。そして「関心・意欲・態度」をこれと対立的に提示することで、これからは「関心・意欲・態度」を中軸にすえた「新しい学力観」に基づいて評価がなされるべきだと主張される。そもそも「知識」や「理解」をこのように通俗的にとらえること自体が誤りであるし、実際には、関心や意欲そしてそこから自然にあらわれる態度と知識や理解とをそれぞれ別個のものとして、到達度を計ることは出来ない。そもそも、興味や関心とは理解や表現や判断が互いに深め合うなかで、引き出されてくるのではないだろうか。つまり「わかる」「出来る」があって「やる気」が沸いてくることは少なくないはずである。これらは無関係に存在するものではないし、何より教師が出来得る仕事は飽く迄、何かを知らせることだけである。直接にある感情を持たせることなど出来はしない。感情や態度を養おうとするにしてもそれはその生徒がそのとき置かれている様々な環境によって大きく左右されるものであるのだから、私たちは何かを知らせることを通じて、生徒の内面にそれらがわき起こってくるのを期待することが出来るだけである。
何も無いところから突然に「関心」や「意欲」や「態度」が出てくることは無い。ある情報が目の前に示されて、それを解釈しようという「関心」がうまれ、その解釈内容によって引き出される感情を「意欲」と呼び、解釈するおおよその方向性を「態度」と呼ぶのではないのか。つまり学習者自身がその内面において、学習を何だと思い、どう意味づけるか、この学習行為をどうみなしているのかとうい学習者自身の認識の問題との関わりを無視して、こちらで設定した「目標に準拠」して「関心・意欲・態度」を学習者から切り離して点数をつけることは本来不可能であるし、無理に実行すればそれは学習者自身の情動を土足で踏みにじることにすらなりかねない5。そしてこの「評価」に生徒が順応したとればそれは、上辺だけの「関心のあるふり」「意欲のあるふり」「良い態度のふり」を学習させることにつながるのではないか? 昨年度の高校への新入生のなかにそのことを裏付ける様子がすでにささやかれ始めているのではないだろうか。
県教委の言葉を借りれば、「関心・意欲・態度」といったものに「評価規準(ノリジュン)」を設定することは出来ても、「評価基準(モトジュン)」を設定させようとすることは根本的誤りでなのある。
観点別評価のやり方については次のようにも書かれている
| 教員の主観に流されずに出来るだけ客観的で信頼性の高い評価を行うためには…具体的な評価規準を設定し…」「評価の目的に応じて評価する人、評価される人、それを利用する人が、互いにおおむね妥当であると判断できることが信頼性の根拠として意味をもつ…評価規準や評価方法等に関する情報を生徒や保護者等に適切に提供し共通理解を図る…(『高等学校における観点別学習状況の評価』) |
などとされている。しかしどうやったら、ある生徒が「関心を持ったか」「意欲を持ったか」を「主観に流され」ないで、「客観的」に判断するための「基準」を作ることが出来るのだろうか?
『指導要録』の改訂についての局長「通知」では、
| この欄には、指導要領に示す各教科の目標に照らして、その実現状況を観点ごとに評価し、A、B、Cの記号により記入すること。 A-「十分満足できると判断されるもの」 B-「おおむね満足できると判断されるもの」 C-「努力を要すると判断されるもの」 |
となっている。県教委は高校もこれに準ぜよという。1人の生徒がどの程度「関心を持ったか」「意欲をもったか」を教師も生徒もその保護者もその他の第三者までもが「おおむね妥当であると判断」できる「評価規準や評価方法等」を設定し、教師が「十分満足できる」なら「A」。「おおむね満足できる」なら「B」。「努力を要する」なら「C」という具合に評定せよと言っているのだがそんなことは出来るのだろうか? 『高等学校における観点別学習状況の評価』では「一般的に見えにくい学力と称される『関心・意欲・態度』」と認めざるを得ない」から、「観察法や面接法をはじめ、課題レポートの取組状況やポートフォリオ評価等の多様な評価方法を工夫」すれば見えるようになると断言している。しかし、これらの方法をつかったとしても、その他どんな方法を使っても観察・評価者である教師の恣意的な満足感による「評価」にならざるを得ない。だからこそ小・中学校では「関心・意欲・態度」の評価法について悩み、「工夫」がなされた結果、手を挙げた回数、発言した回数、はては手を挙げた時の指の動きまでをも数値化し何とか記号付けをせざるを得なくなっているのだ。しかし、このような観察で計測できるのは飽く迄「態度」であって、ここから「意欲」「関心」を計測するのは明らかに誤りである。もしこのような簡単な方法で、誰もが「妥当と認める客観的な」数値化が「関心」や「意欲」などの人の心情について可能なら、そのことが心理学や、脳科学における長年にわたる論争や研究対象になりはしないだろう。それほど人間の情意面を客観的に判断する「基準」を作るのは難しく今日においても不可能なのである。それでもやるというのは「いいかげんに誤魔化せ」と言っているに等しい。
* 人間の情意面までをも『指導要領』の枠の中に閉じ込めることになる。
「新しい学力観」は「自ら学び自ら考える力」をはぐくむことを謳っていた。しかも、「観点別評価」は「目標に準拠した絶対評価」である。教師が学習指導要領に則って「関心・意欲・態度」の目標(評価規準)を設定し、それに沿っていれば「A」で、はみ出していれば「C」とするのである。これでは生徒の内心的活動すら学習指導要領や教師が設定した目標の範囲内に閉じ込めてしまうことになるのではないか? たとえその子が「自ら学び、自ら考え」ようとしても、それがあらかじめ設定された「関心・意欲・態度」の枠からはみ出していれば切り捨てることになりはしないか?
例えば、数学の「関心・意欲・態度」観点は「…数学の論理や体系に関心をもつ…」ことだとなっているが、数学とは論理や体系だけから成っているのではない。イメージや直感、計算技術、背景となる思想・哲学、視覚的感覚やその美しさ、様々な面を持っており、そのどれに魅力を感じ、関心を寄せるのは本人の自由でなければならない。その自由が確保されなければ、それこそ数学への「関心・意欲・態度」の窓口がそれだけ閉められることとなる。「論理や体系」(数学の中で重要な位置を占めるのは確かだか)のみが正統とされれば、その他の実に豊かな数学観と数学への関心には「C」が付けられるのか?なんとも矛盾している。
5. 「観点別評価」(特に「意欲・関心・態度」)が齎すもの
* 「利口なハンス」が作られる
「利口なハンス6」と呼ばれたある馬の事件がある。ハンスの飼い主は1900年代初め頃ドイツのベルリンに住んでいたフォン・オステンという紳士であった。当時ハンスは算術計算ができるということで紙面をにぎわせていた。事実簡単な質問には蹄を鳴らして答えることができた。たとえば、「64の平方根は」と聞かれると、ハンスは蹄を8回鳴らす。ハンスの特技は多くの人々を魅了し、心理学者や動物学者の調査団までが乗り出し「8歳の人間の知能をもっている」と結論された。フォン・オステンはハンスに何らヒントを与えていないと誓ったし、事実、ハンスのこの驚くべき能力を利用して金を稼いだりはしなかった。
しかし心理学者専攻の大学院生であったオスカー・ブフングストは、ハンスの能力に疑いを抱いた。彼は一連の実験を企画し、質問する者が答えを知らなければハンスは正確な答えをだすことができない、ということを証明した。
そればかりか、ハンスは質問者の顔が見えないと、答えることすらできなかった。ブフングストは、ハンスの蹄の動きを開始させたり停止させたりする微妙な手がかりがたくさんあることを発見したのだ。質問者がハンスの蹄のほうに視線を落とすとハンスは蹄を叩き始める。頭をあげて、眉がぴくりと動くとか、小鼻が動くといったある種の表情を浮かべると、それは叩くのをやめる合図となる。そもそも質問などしていなくても、ハンスはそのように反応したのである。実際ハンスに質問をする場合、観衆はつい蹄に注目してしまう。ハンスはそれを見て喜んで蹄を鳴らし始める。ハンスが“正解”の数だけ鳴らした時、質問者は知らず知らずのうちに頭をあげてハンスと目を合わせてしまう。ハンスはそれを見て足を止める。この逸話が、手品と違う点はフォン・オステン氏自身その「種と仕掛け」に気付いていなかったということである。氏は綿密な訓練カリキュラムを組み、ハンスを教育した。目標どおりの成果が上がり、ハンスは利口になった。しかし、実際にハンスが学んだものはなんだったのか。
ここに象徴されていることは学校現場でつねに注意されなければならないはずのことである。
観点別評価の中でも特に「関心・意欲・態度」が定着した結果、私たちはどんな人間を作ってしまうのだろうか。すでに、小中学校を通じてこの観点別評価に浸されてきた生徒たちがいま続々と入ってきている。かれらは、授業中においても先生が説明している最中に関係なく手を上げて勝手に発言する習慣を身に着けている。挙手や発言の回数、ノート提出等を評価してくれとしきりにアピールする。当然である。なぜなら、彼らはそうすることで内申書で高得点を与えられ、神奈川の「前期入試」を勝ち抜いてきたからである。この経験は「隠れたカリキュラム」として、「解からなくてもいいよ」、「そんなことに我慢しなくていいよ」と彼らにささやき続けてきた。結果彼らは方程式の意味を知らなくても、その解き方を知らなくても、「興味」がある「態度」さえ示せば、教師にそういう印象を与えることさえうまくやれば、評価されてきたからである。本当なら、理解し、それをつかって自分で表現が出来るようになることで、面白さを感じ関心を抱くのだとしても、前述した評価の「管理統制的側面」とあいまって、そういう面倒なプロセスを拒否するようにさえなっているように感じる。
しかし「観点別評価」の推進者は言うかもしない。「先生が授業中の発言回数を評価に入れるようになったことで、その授業では、大半の生徒が、自ら挙手して、積極的に発言している。授業は、生徒の発言で進み、とても活気のある授業になっている。もちろん、この活気は、生徒の純粋な学習意欲からだとはいえないかもしれない。しかしたとえそうだとしても、自ら手を挙げて発表しているうちに、苦手意識を払拭することができ、間違いを恐れず発言することができるようになるかもしれない」と。しかしほとんどの場合こう簡単にはいかない。なぜなら、脅迫的に発言を強いることは、何でも良いから考える前に発言することを促す。そのような無思考の発言によって授業が進められるならそれは中身の無い授業であり、なんの前進ももたらさないからである。少なくともそのような状態になりやすくなる。
そして、前述した通り、「統制的機能」を評価が持っている限り、評価はこれまで以上に生徒を脅迫し続ける。
* 教育内容への実質的統制がもたらされる
また現状の超多忙化政策とあいまって、教育内容への実質的介入がもたらされることにもなる。昨今学校にヒステリックなほどに強制される諸施策は、教職員の著しい多忙化をもたらし、生徒とかかわる時間が確実に奪われている。そして、ただでさえ『指導要領』などでがんじがらめにされているのに、研究活動への意欲がそがれ、著しい授業改善への妨害ともなってきた。今回そこに「観点別評価」が導入され、酷い多忙化をもたらすことは必至である。そのとき、私たち教員は「観点別」シラバスや「観点別」教材の作成作業をインターネットにアップされていたり、書店に並ぶ観点別準拠の問題集に頼ることになるだろう。事実、過日に教育センター職員による「観点別評価」の講習会を聞く機会があったが、そこでその講師は「皆さん忙しいのでなかなか、シラバスなどを作る時間も無いでしょー。でも心配要りません。これは、ホームページからコピーして少し手を加えたもので、わたしが今朝30分くらいで作ってきたものです」とプロジェクターで、情報科の観点別シラバスや教材を映して見せた。県教委の例示するものはもとより、業者が作成する教材やシラバスは、国家や支配的世相に従うばかりか、先取りする形の教材しか作れない仕組みになっており、そこからは批判的視点・思考は追い出される。だからこそ、「教育の独立」が原理として確認されてきたのであるが、反対にそれらへの従属がよりいっそう、進められることになる。しかも、これの恐ろしいところは、現場の教師がそれに抵抗し、従属を強制されるのではなく、自ら進んで、批判的精神を投げ捨て、自ら考え悩むことを放棄することである。
直接に教育を司る教職員が、自分たちの目でより広い視野を獲得し、直接に生徒と接することで思い悩み、意見をぶつけ合って教育実践を積み上げていくことが出来なくなる代わりに、ただ「上」からの指示の実行部隊となったとき。社会にとってこれほど恐ろしいものは無い。それは歴史が証明するところである。
6. 通知表を観点別しなければならないのか?(法的側面から)
実施する法的制度的論拠としては、県教委は『指導要録の改善等について(通知)』を出している。しかし、その中でも「評定に当たっては,ペーパーテスト等による知識や技能のみの評価など一部の観点に偏した評定が行われることのないよう四つの観点による評価を十分踏まえながら評定を行っていくとともに,5段階の各段階の評定が個々の教師の主観に流れて客観性や信頼性を欠くことのないよう学校として留意する」となっている。そして、より多くの資料が提示できることによって保護者などへ説明責任がよりいっそう充実することも目的のひとつされている。しかし特に「関心、意欲、態度」といったものは客観的基準によって数値化することが不可能であり、不公平感や不信感を生む。このことから(授業計画段階での観点別はあったとしても)通知表を観点別でやるのはこの『改善通知』にすら反する。また『改善通知』は「各教科・科目の評定については,「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の四つの観点による評価を十分踏まえる」といっているだけで、どこを探しても通知表を観点別でやれとは書いていない。指導要録の様式についても小・中には観点別の欄があるが、高校のものにはそれすら無い。
そして神奈川県が高等学校においては全国に先んじての導入である。つまり前例すらないことを付け加えておく。
7. おわりに
たしかに、これまでの評価は羅列された情報の量をテストによって測るだけになりがちであった。これは見直されなければならないだろう。本当の意味で、より理想に近い評価と学力観、それらと双対の関係にある授業形態の改善は運動として追及されるべきだし、それを強く意識した実践が積み重ねられねば成らない。しかしそれは、これまで見てきたように上からの力によって「学力」の定義を変え、それに従った「点数付け」=「順序付け」による選別と統制を強化することで解決されるであろうか? それは問題の本質を隠蔽することにしかならない。学校本来の使命は知識の伝達を通して、「民主的で文化的な国家」の形成者として「人格の完成」の一助となすことである。それを放棄したとき学校は何になるであろうか?
かつて知識が一部の特権階級の独占物であり、支配される側は無知という頚木をはめられていた。それを取り払い、かれらの生活と思想を解放することが学校の果たすべき役割であったはずである7。このことが今こそ思い起こされる必要があるのではないだろうか。
このように振り返って見るとこの課題は本来ならば、10数年前「新しい学力観」と共に「観点別評価」導入が噂されたときに、組合の内的、外的にも議論を重ね、導入反対の運動を提起し、そのなかで市民へも疑問を投げかけ、警鐘を鳴らすべきであったと感じる。そうならなかった背景には「評価権はどのようなことがあろうとも、教師の手を離れることはありえない」という、今となって見れば反省されるべき認識の甘さもあったのかもしれない。
昨今は、議論する間もなく、つまりそれが何でありどのような問題点を持っているかの分析もなされず、しかしなんとなくの疑問と徒労感と諦めを引きずりながら、あらゆることが離れた所で進んでいくように感じる。このようなときだからこそ、導入必至とはいえ、盲目的に職務を遂行するのではなく、疑問と批判の視点を忘れずに、すぐにどうにかなるものではないかもしれないが批判の種を撒き、耕すことが意識的に追求されなければならないのではないだろうか。そのために、今後、今回の「観点別評価」を実施していく中でも、様々な困難や課題を実証的に積み重ねる作業が必要になると考える。そのために継続的に学習会または研究会をもち、私たちの教育論と本当に必要な評価論を構築し、それが現場に渡ったときに理論的武器となるまでに鍛え上げ、それを広める戦術と策略を検討していくことを提起したい。もちろんこれは、高校だけでは本質的反対運動にはなりえない。小中高教育労働者全体の視野に立たなければならない、したがって広範な協力関係を必要とする取り組みとならなければならない。
参考文献
・ 高総検 『高総検報告Ⅷ―新多様化・総合学科・新学力観』 1995/2
・ 駒林邦男 『現代社会の学力』放送大学教材 1997
・ アンドリュー・D・ホワイト(森島恒雄訳) 『科学と宗教との闘争』岩波新書
・ 宇沢弘文 『自動車の社会的費用』岩波新書
・ 同 『日本の教育を考える』岩波新書
・ 原田琢也 『大阪教法研ニュース 第167号』1996/7 http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/
・ 藤田英典 『教育改革』岩波新書 1997
1 三浦 朱門(みうら しゅもん、1926年1月12日~)は作家。第7代文化庁長官。教育課程審議会会長を歴任。現在は日活芸術学院の学長をつとめる。東京都出身。東京大学文学部言語学科卒業。2000年7月、ジャーナリストの斎藤貴男に、「ゆとり教育」の本旨は“100人に2~3人でもいい、必ずいる筈”のエリートを見つけ伸ばす為の「選民教育」である事を明言。教育課程審議会においては、「ゆとり教育」をめぐり「私は今まで数学が私の人生に役立ったことは無く、大多数の国民もそうだろう。」と発言。当時の文部事務次官の意向に沿った発言を行ない、以後の「ゆとり教育」を加速させた。2004年2月、『文藝春秋』3月号で自衛隊のイラク派遣の是非を問うアンケートに、「もし戦死者が出れば、それは憲法改正のための尊い犠牲なのだと考えたい」と回答した。04年9月、日本芸術院の院長に選出された。作家曽野綾子の配偶者。
2 ここでは「学歴」とは言わずに、より正確に学校暦といいたい。本来「何を学んできたか」と「どの学校に通っていたか」は別の話である。
3 ちなみに経済学者宇沢弘文はこの点について「社会的共通資本」という概念をもって論じている。「社会的共通資本というのは、人間の尊厳、自由を守るというリベラリズムの立場を具体的な経済的制度として実現するためのコアになる概念」であるとして「基礎教育にかかわる諸々の人間的能力、物理的施設、制度的諸条件は社会的共通資本としての特質を持っていて、学校をはじめとして基礎教育を提供する組織、制度は決して市場的基準あるいは利潤的動機によって左右されてはならない」のだといっている。(『自動車の社会的費用』、『日本の教育を考える』/岩波新書 より)
4 そもそも評定とは、目標に達しているかを関係者で話し合う「ひょうじょう」からきていて、観点別評価の数値的操作のような形式的な作業をあらわす概念ではない。
5文字通りの「内心の自由」の侵害である
6 これは教育心理学で言うところの「隠れたカリキュラム」を説明する有名な例である。
7 最近の教育論は、目先の実用的な側面ばかりが強調されているように感じる。そのためとくに数学・科学教育については、「専門に進む者だけに施せばよいのだ、その他には必要ない」という声も大きい。しかし、ここで述べている教育の本来的目的からすれば、そのような考えは非常に危険である言わなければならない。
幾度と無く繰り返される「文明社会」でのあらゆる野蛮は、常に非合理を必要とする。したがって野蛮によって自らの地位をやっと守れるものたちにとっては数学や科学がいつも敵であった。このことは魔女狩りや主教裁判、ホロコーストなどの歴史が証明するところである。だからこそ彼等は、科学・数学への何らかの新しい貢献をなした殆どの何人にたいしても「無心論」、「不信者」などの武器で直接に攻撃を加えたし、またはそれらが大勢の人間に広まり、合理的で体系的な考え方を獲得することを恐れた。この原理は今日においても変わらない。大勢の人間を惨めな目に合わせる政府は、民衆がその惨めさと政府との関係を合理的に考えはじめることを何とかして避けなければならない。(もちろん藤原正彦や河合隼雄のような例も在るから数学・科学教育だけでは足りないのも事実である)。
ところで、宗教(搾取階級のイデオロギーとしての)と科学の何十世紀にもわたる激烈な闘いの歴史をもつ欧州では、その歴史的教訓が少なからず反映されているようである。たとえば、日本のセンター試験とよく比較されるフランスのバカロレア試験(後期中等教育修了資格試験)では、マーク式試験などではなく、哲学の試験はもとより、数学でも(むしろ「だからこそ」というべきか)しっかりとした論証も伴って答えられていなければ合格点が得られないと聞く。そしてこの試験が民衆知識の一定水準を維持するのに役立っている。もちろんこのバカロレアを廃止し、選択肢の多い「多様」な試験に変えようという動きが過去何度かなされたそうだが、(現在では「職業」・「技術」・「普通」の3つのバカロレアになっているとはいえ)その都度教師と学生とが一体となった反対運動で阻止されてきた。昨年2月にも、「試験科目を半減させる代わりに在学中の平常点を加えた総合判断にする」という政府案に対して、「相対評価の導入は学校間差別を拡大させる」と反対運動が起こり全国の高校生10万人(25万人という話もある)がデモを行い、これを阻止をした。それこそ日本とは「学力観」が違うのである。
残念ながら現在、日本の数学・科学教育はそのあるべき目的からすれば、かけ離れたところに在る。そしてそれは数学・科学教育に限った話でもないだろう。なにしろ、脚注1にも書いたことだが「私は今まで数学が私の人生に役立ったことは無く、大多数の国民もそうだろう」などと平気で公言する人間が教育審議会会長を勤められるのだから。フランスとは同じ「バカ」が付くとしてもだいぶ違う。