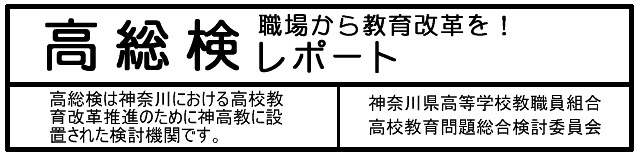
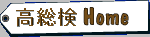

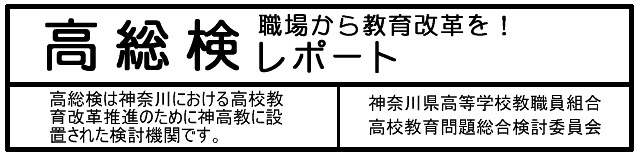
(はじめに)
安倍晋三首相は1月26日、施政方針演説の中で「教育再生は内閣の最重要課題」と明言した。その中で強調されたのは、予想通り、道徳教育の充実など「改正」教育基本法を踏まえた公教育の「再生」に取り組むことである。また、憲法改正の準備として改憲手続きを定めた国民投票法案の今国会成立を目指すが、ねらいは「戦後レジーム(体制)」からの脱却である。
「教育再生」のための法案として提出が予定されている関連法案が内容とするのは、(1)ゆとり教育の見直し(2)学習指導要領の改訂(3)教員免許更新制の導入(4)教育委員会改革、である。このレポートでは安倍内閣発足時から話題になっていた「教育バウチャー制度」について考えていきたい。
(教育バウチャー制度導入の「論理」)
昨年9月の発足時、安倍内閣の掲げる「教育改革」の項目の中で「教育バウチャー制度」は目玉商品として挙げられていた。彼は著書『美しい国へ』で「格差の再生産を防ぐ対策の一つ」としてこの制度を紹介する。ニート・フリーター問題の原因を教育における格差の再生産に求め、貧しい家庭の子女でもこの制度を利用すれば私立学校に進学できるようになる、というのである。
安倍首相は内閣を組織すると早速「教育再生会議」を立ち上げ、「教育改革」の推進役として位置づけた。そのメンバーの一人、外食チェーン・ワタミ社長の渡辺美樹氏は、「教育バウチャー制度」の宣伝マンのようであり、マスコミに向けてことあるごとにこの制度の導入のメリットを語っている。彼は昨年10月、神奈川県の教育委員の一人に選ばれたので、神奈川で何らかの動きをする可能性がある。
彼の発言はある意味で非常に分かりすい。その言によれば、「バウチャー制度」導入のねらいはこういうことになる。
「バウチャー制度は自然に競争原理が働く」「生徒が集まらない学校でも経営が成り立つのは、まずい料理を出してもつぶれない店と同じ」いかにも飲み屋チェーンの経営者の発言である。
(「教育バウチャー制度」とはどのような制度か)
「バウチャー」とは、いわゆるクーポン券のことである。すべての家庭に教育クーポン券を配布しておき、住民に子女を通わせる学校を選択させる。券を受け取った学校は、その枚数によって予算を受け取る、という仕組みである。
この制度を導入することで生じるいちばん大きな変化は何かというと、従来国や自治体から学校単位で配分されていた予算が生徒単位で配分されるようになることである。つまり予算配分の基本が変更されるということだ。学校側としては生徒を獲得しなければ予算が確保できないため、生徒獲得競争が起こり、競争原理が働く結果「教育の質の向上につながる」というのが導入側の論理である。
この制度は「学校選択制」の大幅な導入とセットであるのが特徴である。教育を受ける側が自らの意志に基づいて学校を選択するので、どのような教育内容を選ぶかの決定権が受け取る側に移るという発想が、ここには見られる。これが「教育を受ける機会の平等を保障」するという説明になる所以である。
また、従来の一般的な「学校選択制」との違いは、学校設置主体への予算配分の違いから「公立」と「私立」を分けていた壁を突破することである。教育バウチャー制度の導入によって、補助金が公私の別なく入学する子どもの数に応じて配分されるので、「公私格差は理論的になくなる」と推進側は説明する。ここには、私学援助=公立学校つぶしの野望も覗いている。
(サッチャー流の自由主義的改革)
安倍首相は、イギリスのサッチャー首相の行った教育改革を高く評価している。保守党のサッチャーが目指したのは、徹底した民営化、市場原理導入による「小さな政府」の構築であった。「教育バウチャー制」はイギリスで1988年から始まった教育制度改革の一環として導入されたものである。統一学力テストを実施して全国規模の成績到達目標の設定により学校を自由競争にさらし、全体の学力を底上げするという狙いがあったが、現在では保守党内部からも教育改革は失敗だったとの反省が強まっているという。各学校は「統一テストの平均点を落とさない対策」にばかり熱心になって、学力の劣る子どもの入学を拒んだり、テスト当日に受けさせないようにしたりするなどの現象が起きた。結果として学校間格差は拡大し、学校の序列は固定化された。学力テストの結果は公表され、衆目にさらされるので下位の学校は校長のなり手さえ見つからない。そこで学力テストそのものの廃止の動きさえ出てきている。
イギリスの「教育バウチャー制」は明らかに失敗している。それを今後日本で導入しようというのは、「学力向上」という表向きの理由以外に隠された理由があるに違いない。それは教育予算の全体的な削減と教育内容への国家の介入である。サッチャー流教育改革で実施されたのも「ナショナル・カリキュラム」による教育内容への中央政府の介入と教育基準局設置による学校査察の強化であった。
(「選択」は住民「参加」を排除する)
ここで「バウチャー制」の前提となる、公立の小中学校における「学校選択」の論理について考えてみよう。それは、生徒や保護者といった地域住民個々人が通学すべき学校を自らの意志で選択でき、そのことで「教育内容の選択」が実現される、という展開になっている。ここには危険な落とし穴が隠されていると言わざるを得ない。
教育内容を地域住民が「選択」するということは、彼らの「選択」という行為に先立って、複数の教育内容が選択肢として「用意」されているということが必然的に前提されてしまう。それでは「用意」するのは誰か?もちろん、それは行政や学校関係者に他ならない。つまり、「選択」を前提とするシステムは必然的に、選択すべき対象に対する主体的なコミットメントを排除する、ということだ。
従来民主的な教育の在り方として理想とされてきたのは、子どもや保護者といった教育を受ける権利主体自身が「内容についての決定」に関わることができる、ということだったはずである。「国民の教育権」はこうした文脈で語られてきた。それに対して「学校選択制」は、教育を受ける側を、初めから第三者の位置に貶めるものである。地域住民の教育内容への決定権が保障されている場合、少なくとも「選択」という発想は生まれてこないだろう。「選択」はあくまで「外部から」対象へアプローチするときの概念であり、「内部から」のアプローチを意味する「参画」や「決定」とは異質の用語である。
したがって、「選択」が強調されるとき、そこには常に危険なトリックがあることに注意を払うべきだろう。「学校選択」は、確かに言葉のニュアンスにおいては住民側に地域の教育に対する主体的な関わりを保障するようなポーズを取りながら、実は住民を欺いて行政側の操作対象に陥れてしまう。
我々は「学校選択」という卑近な関心事に気を取られて本質的なものを見失ってはならない。もっと大切なものは、教育を受ける主体として「教育内容の決定」に関わる権限である。我々が本来もつべき地域の教育活動に参画する権利を、「教育バウチャー制度」がかすめ取っていく危険性があることに注意をすべきである。こうした意味で、「学校選択制」は「国民の教育権」の対極に位置する。
(「学校選択制」「教育バウチャー制」は地域共同体の基盤を破壊する)
日本の歴史の中で、また海外の例を考えてみても、小中の公立学校は「わが町の学校」として地域社会の協力の中心に位置付けられ、地域の連帯を形成する精神的な基盤となって発展してきた。近隣の子どもたちが誘い合わせて登校するのを付近の住民が温かい目で見守る風景は、ともに地域社会を担っている者の連帯感を感じさせるものであった。その意味で、地域の学校は単に子どもたちの狭い意味での教育の目的にのみ存在する場所ではない。
現代において首都圏から遠く離れた過疎地で典型的に見られるように、地域の学校の閉校は地域住民にとっては地域の文化の火が消えることを意味する。学校は地域住民が様々な形で集う場所であり、学校行事は地域住民にとっての行事という意味合いをもっているからである。もっとも最近では東京の都市部において小中学校の統廃合問題が次々生じており、地域の文化を長い間にわたって培ってきた住民側と行政の対立が見られる。「学校選択制」は地域環境をどのようにつくっていくべきかという地域行政のありかたと密接に関わる問題でもある。
地域の公立学校を地域のコミュニティーの活力を再生産する装置としていかに位置づけるかという問題が問われているというべきだろう。「学校選択制」「教育バウチャー制」は必然的に「学校」と「地域」を引き離しにかかる。「学校」は「地域」に支えられて存在するものという性格が奪われ、単にたくさんの選択肢の中から自らの志向に合わせて「選択」される対象となる。
現代のコミュニティーを辛うじてつなぎ止めている「地域の学校」という最低限の紐帯が「教育への市場原理導入」の名の下で脆くも解かれる。このことは都市部においてはむしろ実態を追認するという意味しかもち得ないと考える向きもあろう。地域住民はよって立つべき「地域社会」という基盤をもうすでに持っていないという判断である。
「(教育バウチャー制」導入でどう変わる?)
もし「学校選択制」や「教育バウチャー制」が導入されたとして、「選択」の対象から除外されてしまうような学校とはどういう学校だろうか。それは「荒れる学校」だったり、「生徒が落ち着いて学習に取り組んでいない学校」だったり、要するに保護者の立場から見ると自分の子どもの学力形成には不利とみなされる学校だろう。そのような学校は、少し経済的に余裕のある保護者によっては選択されないことになる。
公立学校がそれぞれ異なった事情をもつ地域を背景に立地しているのは当然である。そこに通学してくる子どもたちの学力が家庭や地域の経済状態を如実に反映していることは、我々高校現場に身を置くものは感覚的に知っている。21世紀に入ってからの小泉構造改革の影響が所得格差を益々拡大する方向に進み、就学援助等の予算が増大していることもマスコミによって報じられている。
もし、家庭環境・地域環境を考慮することなく、単に「学力」という指標のみで「学校の評価」を測るということになればどうなるか?それは簡単に予想がつくことだ。平均所得の低い地域を学区としている公立学校は「学力が劣る」という評価になる。「学校選択制」(=バウチャー制)の判断材料として予定されている「学力テスト」は地域から「学力の低い学校」を切り捨てていく効果を発揮する。「低所得階層」は、いわば現代日本社会から2回も切り捨てられるのである。
このやり方をもって「学校の改善」「教育改革」と呼ぶことができるのだろうか?現代社会に存在する問題に巧妙に目隠しする、そのことをもって「解決」と名づけるならば、「市場原理」というものは真に過酷な原理である。
(「教育バウチャー制」は家庭経済・地域経済の破壊、そして「教育の機会均等」に違反)
「教育バウチャー制」が導入されれば、平均所得の低い地域に立地する公立学校は閉校に追い込まれていくだろう。そうなると、その学区の子どもたちはわざわざバスや電車など交通手段を利用して遠くの学校に通学しなければならなくなる。このことは家庭に対して余計な経済的負担を強いることになる。1日子ども一人当たり数百円、月額で数千円から1万円ほどの交通費が発生し、経済的な負担が家庭に重くのしかかる。そのダメージは経済的に貧しい家庭であればあるほど影響が大きくなる。
これは明らかに「教育を受ける権利」の侵害であり、「教育の機会均等」の原則の破壊ではなかろうか。
一方で、「教育バウチャー制」で選択から外れた学校用地は民間資本に払い下げられ、再開発事業の対象となって該当企業が利益を上げて超え太っていく・・・。東京都文京区では08年度から11年かけて小中31校を21校に減らす計画が進行中で、地域住民の間から反対の声が起こっている。学校の統廃合と公園・体育館、教育センターの移転・新築で500億円の事業規模となるという試算もある。もし、学校の統廃合の前に「学校選択制」や「バウチャー制」が実施されれば、地域住民には反対する理由がなくなる。
昨年11月、朝日新聞の報道で全国的な話題となった東京・足立区の「学校格差予算」は、07年度予算で計画通り実施されるという。足立区はもうすでに学力テストの成績を学校ごとにホームページ上で公開している。住民はそのデータを見て進学先を決める。中には過去問を何度も練習させて学力テストの平均点を上げる努力をしている学校もあるらしい。(『週間東洋経済』2007.1.27号)
これが「教育への市場原理導入」の過酷な未来像だ。